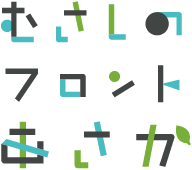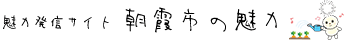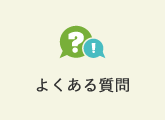本文
税の申告は正しくお早めに(令和8年度(令和7年分))
税の申告が必要な方、判断基準
個々人の状況に応じて、税の申告の方法が異なります。
1 所得税の確定申告が必要な方、したほうがよい方
<給与所得者の方のうち>
・給与収入が2000万円を超えている方
・勤務先で年末調整をしていない方
・主たる給与および退職所得以外の所得が20万円を超えている方
・医療費控除など、各種控除を追加する方
<公的年金を受給している方のうち>
・公的年金収入が400万円を超えている方
・公的年金以外の所得が20万円を超えている方
・医療費控除など、各種控除を追加する場合で、源泉徴収税額がある方
<営業、不動産、農業、雑所得(公的年金以外)、一時所得などがあった方>
・原則、確定申告が必要ですが、所得税に影響がない場合は市民税・県民税の申告が必要です。
※令和8年1月1日現在の居住地が朝霞市外であっても、朝霞市内に事務所・事業所等を有している方は申告が必要です。
2 市民税・県民税の申告が必要な方、したほうがよい方
※確定申告を行う場合は、市民税・県民税の申告は必要ありません。
<給与収入がある方のうち>
・勤務先から市役所に「給与支払報告書」の提出がなされていない方(提出の有無は勤務先にご確認ください。)
・給与および退職所得以外の所得があるが、20万円以下の方
<年金収入がある方のうち>
・公的年金以外の所得があるが、20万円以下の方
・源泉徴収税額がなく、源泉徴収票の記載内容では市民税・県民税の非課税基準(※1)に該当せず、控除を追加する方
<収入がない方や非課税所得のみの方のうち>ー収入が無い旨の申告が必要な場合がありますー
・同一世帯のどなたかの税法上の扶養として申告されていない方
・配偶者の税法上の扶養になっているが、配偶者の合計所得金額が1000万円を超えている方
3 ご申告の必要がない方
上記に該当しない方
<例>
・給与所得者だが、年末調整が済んでおり、それ以外に申告する所得や控除がない方(※2)
・公的年金所得はあるが、市民税・県民税の非課税基準(※1)に該当する方
・同一世帯の税法上の被扶養者になっており、収入もない方
※1 市民税・県民税の非課税基準とは、その年の合計所得金額や扶養人数等の状況によって、市民税・県民税が非課税となる基準を言います。
例えば、扶養親族がいない方で、自身が障害者である等の一定の要件に該当しない方の非課税基準は、合計所得金額が45万円以下となります。非課税基準に該当する場合はその年度の市民税・県民税は非課税に、それを超える所得がある方は課税されることとなります。
※2 勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がなされていない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。
個人住民税申告の電子化について
令和8年度分(令和7年中の所得)の申告分からスマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して個人住民税の電子申告ができるようになります。申告システムは24時間(システムのメンテナンス時間を除く)利用できますので、ぜひご利用ください。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
郵送での申告について
市民税・県民税の申告書(朝霞市役所宛て)は郵送提出が可能です。
簡易な申告については、こちら(市民税・県民税申告書の記入例)をご参照ください。
<市民税・県民税の申告書>
昨年度、市民税・県民税の申告をされた方には、2月2日(月)に申告書をお送りいたします。
そのほか、申告書が必要な方は、個別に郵送いたしますので、お電話にてご連絡ください。
申告期間と会場
| 受付会場 | 受付期間および時間 |
|---|---|
|
市役所別館 |
2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)(土・日曜日、祝日を除く) |
市民税・県民税の申告のほか、給与所得者および年金所得者の所得税確定申告についても、上記のとおり受け付けています。
※収入がなかったことの申告については市役所2階21番課税課市民税係でも受付を行います。
※事業・不動産・譲渡所得・利子所得のある方、所得税の住宅借入金等特別控除の申告等は、税務署での受け付けとなります。
なお、税務署での確定申告については、以下のリンクから詳細をご確認ください。
申告にお持ちいただくもの
| 本人確認資料 | マイナンバーカード |
マイナンバーカードが無い方は、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類 【マイナンバーがわかる書類】 マイナンバーの記載がある住民票または住民票記載事項証明書(もしくは記載事項に変更すべき事項がないマイナンバー通知カード) 【本人確認書類】 運転免許証、健康保険の資格確認書など ※マイナンバーが提示できない方についても、その他の資料がそろっている場合は申告を受け付けます。 |
| 利用者識別番号 |
【過去に確定申告を電子で提出したことがある方】 【確定申告を電子提出したことがない方】 |
|
| 所得の資料 | 給与収入または公的年金収入がある | 令和7年分源泉徴収票 |
| 雑所得、一時所得等の、給与・公的年金以外の所得がある |
所得金額が証明できるもの(収入金額と経費内訳がわかるもの。帳簿類、個人年金のハガキ等) ※営業・農業・不動産・譲渡所得等については、所得金額によりますが、原則税務署での申告となります。 |
|
| 控除の資料 | 社会保険料控除を受ける方 | 令和7年中(1月1日~12月31日)に支払った保険料(国民年金保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者(長寿)医療保険料、介護保険料など)の支払証明書または領収書 |
| 生命保険料、地震保険料控除を受ける方 | 令和7年中(1月1日~12月31日)に支払った保険料の支払証明書または控除証明書 | |
| 障害者控除を受ける方(被扶養者含む) | 障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など | |
| 勤労学生控除を受ける方 | 学生証または在学証明書 | |
| 医療費控除(またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例))を受ける方 |
令和8年度(令和7年分)医療費控除の明細書(またはセルフメディケーション税制の明細書) ※平成29年分から、医療費の領収書では申告をお受けできなくなりましたのでご注意ください。 |
|
| 寄附金控除を受ける方 |
令和7年分の寄附金受領証明書 ※ワンストップ特例制度を申請している場合であっても、申告を行うとワンストップ特例制度の適用ができなくなりますので、寄附金受領証明書を持参してください。 |
ご注意ください
・申告を忘れると、児童手当等を受けるときや保育園に入園するとき、融資を受けるとき、年金の免除申請をするときなどに必要な証明書等の発行ができません。
・収入のなかった方についても、申告をしていただくことにより非課税証明書の発行、国民健康保険税(料)・介護保険料などの算定の基礎資料となりますので、忘れずに申告してください。
・ご家族の方が申告や年末調整の際にあなたのことを税法上の扶養(社会保険などの健康保険の扶養に入ることとは異なります)とする記載が漏れている場合もありますので、ご確認ください。この場合、ご家族の方の申告が必要です。