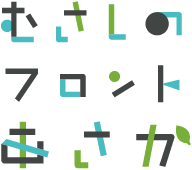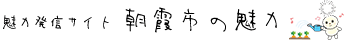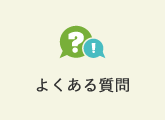本文
FAQ(よくある質問集):国民健康保険
このページでは、朝霞市国民健康保険(以下、国保)に関するよくある質問と回答を掲載しています。
各種手続きに当たっては、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
FAQ(よくある質問集):朝霞市国民健康保険
1 加入に関すること
2 脱退に関すること
3 マイナ保険証または資格確認書に関すること
4 国保税に関すること
5 国保税の減免に関すること
6 高額療養費・限度額適用認定証に関すること
7 療養費(一般診療・海外診療・補装具)に関すること
8 第三者行為(交通事故等)に関すること
9 葬祭費に関すること
10 その他
1 加入に関すること
Q 会社を退職しました。国保に加入するには、どのような手続きが必要ですか。
A 「資格喪失証明書」、「退職証明書」または「離職票」を持って、朝霞市役所保険年金課、各出張所または内間木支所にお越しください。これらの書類があれば、その場で手続きできます。
Q 会社を退職しました。離職票がまだもらえないのですが、国保の加入手続きはできますか。
A 「資格喪失証明書」、「退職証明書」または「離職票」といった書類が届くのが遅い場合などは、保険年金課から会社に電話し、社会保険の喪失年月日がわかれば、加入手続きを進めることができます。
2 脱退に関すること
Q 会社の健康保険に加入しましたが、国保はどうなりますか。
A 国保の脱退手続きが必要です。国保を脱退する全員分の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、マイナポータル画面のいずれかを提示し、脱退手続きをしてください。郵送、朝霞市役所保険年金課、各出張所または内間木支所のいずれかで手続きできます。
Q 会社の健康保険に加入しているのに、国保税の納税通知書が届きました。そのままにしていてもいいですか。
A 次のような場合がありますので、ご確認ください。
1 世帯の中に国保被保険者がいる場合
世帯主自身が国保に加入していなくても、その世帯の中に国保加入者がいると、国保税は納税義務者である世帯主に課税されます。
2 国保の脱退手続きをしていない場合
国保加入者が他の健康保険に入った場合、国保を脱退する手続きが必要です。自動で脱退とはならないため、脱退手続きをしないと、国保に加入したままの状態が続くことから、国保税が課税されるほか、滞納があれば延滞金が発生してしまいます。
3 国保の脱退手続きをした場合
脱退手続きをした翌月に、加入期間に応じて、国保税を再計算します。
Q 会社の健康保険に加入しているのに、国保で病院を受診してしまいました。そのままにしていてもいいですか。
A 本来、国保の資格で医療機関を受診することはできません。医療機関に、国保ではなく会社の健康保険であることをお伝えください。また、次のような場合がありますので、ご確認ください。
1 診療報酬明細書(レセプト)が朝霞市に届いた時点で国保の脱退手続きをしている場合
国保の資格なしとして、レセプトを医療機関に返戻します(朝霞市から医療給付費分を医療機関には支払いません)。
2 レセプトが市に届いた時点で国保の脱退手続きをしていない場合
国保の資格が残ったままなので、朝霞市から医療機関に医療給費分が支払われてしまいます。至急、国保の脱退手続きをしてください。その後、朝霞市が医療機関に支払った医療給費分を、医療機関ではなく、ご本人に返還していただきます。朝霞市から返還をお願いする通知(返納通知)と納付書が届きますので、期限までにお支払いください。
なお、脱退手続きをしてから、返納通知が届くまでに、4か月程度かかる可能性があります。
3 マイナ保険証または資格確認書に関すること
Q マイナ保険証とは何ですか。また、資格情報のお知らせとは、何ですか。
A マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしたものです。登録方法などは、マイナンバーカードと健康保険証の一体化のページをご覧ください。
また、資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方が、自身の健康保険に関する記号・番号などの情報を簡易に把握できるように交付している書類(A4サイズ)です。医療機関等を受診する際は、マイナ保険証だけで受診ができますが、マイナ保険証を読み取る端末の不具合などがあった場合は、マイナンバーカードと併せて資格情報のお知らせを提示することで、保険診療を受けられますので、大切にお持ちください。
Q 資格確認書とは何ですか。
A 資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方に交付しています。従来の健康保険証と同様に、資格確認書を提示することで、医療機関を受診することができます。
なお、従来の健康保険証と同じカード型で交付しています。
Q 資格確認書が届きません。
A 次のような場合がありますので、ご確認ください。
1 他の郵便物は届いている場合
マイナ保険証をお持ちの方には交付していません。マイナ保険証の利用登録状況は、マイナポータルで確認いただくか、保険年金課までお問い合わせください。
また、資格確認書は、初回の交付は簡易書留、2回目以降は特定記録で、世帯主宛てに送付しています。他の郵便物に紛れていたり、世帯主が持っている可能性がありますので、ご確認をお願いします。
2 他の郵便物も届いていない場合
郵便物すべてが宛て所なしとなっている可能性がありますので、郵便局にて居住登録の上、保険年金課までご連絡ください。
Q マイナ保険証を使用しており、資格確認書も欲しいのですが、どうすればいいですか。
A マイナ保険証をお持ちの方には、念のため持っておきたいといった理由では資格確認書は交付していません。障害があったり、施設に入所している等の理由により、マイナ保険証が利用できない場合は、保険年金課にご相談ください。
Q マイナ保険証の利用をやめたいのですが、どうすればいいですか。
A 保険年金課で、マイナ保険証の利用をやめる手続きをしてください。受付後、「資格確認書」を世帯主宛てに郵送します。
4 国保税に関すること
Q 国保税額を試算して欲しいのですが。
A 試算表に、実際の所得金額等を入力することで、国保税額を試算することができます。
Q 国保に加入していないのに、世帯主が国保税を払わないといけないのですか。
A 国保税の納税義務者は、国保加入者のいる世帯の世帯主です。よって、世帯主本人が国保に加入していなくても、その世帯の中に国保加入者がいれば、その世帯主が納税義務者となり、国保税が課税されます。
Q 国保の世帯員ごとに国保税を払いたいのですが、どうすればいいですか。
A 国保税は、世帯主が納税義務者であるため、世帯内の国保加入者一人一人に納付書を分けることはできません。しかしながら、加入者ごとの国保税を計算することはできますので、保険年金課にお問い合わせください。
Q 昨年は年金から国保税が天引きされていましたが、今年は天引きされないのはなぜですか。
A 年金から国保税が天引きされる方は、次の1~3のすべてに当てはまる方のみです。
1 世帯主が国保加入者であり、介護保険料が年金から特別徴収されていること
2 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。※75歳になる年度は年金特徴されません。
3 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
Q 国保税の納税証明書が欲しいのですが、どうすればいいですか。
A 収納課で発行しています。詳しくは、税の証明のページをご覧ください。
5 国保税の減免に関すること
Q 会社を退職しましたが、国保税は減免されますか。
A 倒産、解雇等により離職された方に対する軽減措置があります。
【対象となる方】
離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかの方。ただし、雇用保険受給資格者証の右上に、「特」「高」の表示がある方は対象となりません。
【手続きに必要なもの】
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、本人確認書類
6 高額療養費・限度額適用認定証に関すること
Q 医療費の支払いが高額になりそうですが、どうしたらいいですか。
A マイナ保険証による受診であれば、医療機関等の窓口では限度額が適用された金額までの支払いとなります。また、マイナ保険証を持っていなくても、医療機関等でオンラインで資格の確認ができる場合は、同じく限度額が適用された金額までの支払いとなります。
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際は、事前に限度額適用認定証の交付申請が必要です。
なお、国保税の未納がある場合は、限度額の適用はできません。
Q 医療費が高額になったので、高額療養費の申請をしたいのですが、どうしたらいいですか。
A 高額療養費の支給申請ができる世帯には、保険年金課から申請案内を世帯主宛て送付します。案内が届いたら、保険年金課で支給申請の手続きをしてください。
なお、高額療養費は対象の診療年月の翌月から2年経過すると、申請の受付ができなくなりますので、案内が届きましたら、お早めに手続きをしてください。
(例)令和7年4月診療分の高額療養費は、令和9年4月30日までに申請が必要
7 療養費(一般診療・海外診療・補装具)に関すること
Q 会社の健康保険に加入しているのに、国保で病院を受診してしまいました。そのままにしていてもいいですか。
A 本来、国保の資格で医療機関を受診することはできません。医療機関に、国保ではなく会社の健康保険であることをお伝えください。また、次のような場合がありますので、ご確認ください。
1 「診療報酬明細書(レセプト)」が朝霞市に届いた時点で国保の脱退手続きをしている場合
国保の資格なしとして、レセプトを医療機関に返戻します(朝霞市から医療給付費分を医療機関には支払いません)。
2 レセプトが市に届いた時点で国保の脱退手続きをしていない場合
国保の資格が残ったままなので、朝霞市から医療機関に医療給費分が支払われてしまいます。至急、国保の脱退手続きをしてください。その後、朝霞市が医療機関に支払った医療給費分を、医療機関ではなく、ご本人に返還していただきます。朝霞市から返還をお願いする通知(返納通知)と納付書が届きますので、期限までにお支払いください。
なお、脱退手続きをしてから、返納通知が届くまでに、4か月程度かかる可能性があります。
Q 国保の資格を証明できなかったので、全額自己負担で病院を受診しました。どうすればいいですか。
A 申請により、本来の自己負担分(2割または3割)を除いた額の給付を受けることができます。病院から発行された「診療報酬明細書(レセプト)」と、振込先口座の通帳等(世帯主)を持って、朝霞市役所保険年金課で療養費の申請をしてください。
なお、療養費を申請してから振込まで最短3か月程度かかります。医療費(治療に要した費用)を支払った日の翌日から2年経過すると、申請の受付ができなくなりますので、お早めに手続きをしてください。
Q 海外で、全額自己負担で病院を受診しました。どうすればいいですか。
A 国保加入者が、海外渡航中に緊急の病気やけがでやむを得ず治療を受けた場合、帰国後、療養費の申請をすることにより、保険が適用されます。ただし、治療目的で渡航した時には、保険は適用されません。
なお、療養費を申請してから振込まで最短3か月程度かかります。医療費(治療に要した費用)を支払った日の翌日から2年経過すると、申請の受付ができなくなりますので、お早めに手続きをしてください。
1 申請方法
海外で受診した医療機関が記入した「診療内容明細書」「領収明細書」または「領収明細書に準ずる証明書」が必要です(原本のほかに、和訳が必要です)。帰国後、2の必要書類を持って、朝霞市役所保険年金課で療養費を申請してください。
2 必要書類
「診療内容明細書」「領収明細書」または「領収明細書に準ずる証明書」(要和訳)・パスポート・領収書(現地医療機関が発行したもの)・振込先口座の通帳(世帯主)
※ 日本国内で保険適用となっていない医療行為については対象とならないため、現地での支払額に対する療養費の支給決定額が異なることがあります。
Q 補装具(コルセット等)を全額自己負担で購入しました。どうすればいいですか。
A 医療機関が作成した、補装具の製作指示装着証明書および補装具を購入した際の領収書、振込先口座のわかる通帳等(世帯主)を持って、朝霞市役所保険年金課、各出張所または内間木支所で療養費を申請してください。
なお、療養費を申請してから振込まで最短3か月程度かかります。補装具に要した費用を支払った日の翌日から2年経過すると、申請の受付ができなくなりますので、お早めに手続きをしてください。
8 第三者行為(交通事故等)に関すること
Q 交通事故により、けがをしました。国保で病院を受診してもいいですか。
A 国保で受診することはできますが、届出が必要です。医療機関で国保を使用する前に必ず保険年金課まで連絡してください。交通事故でけがをした場合、本来その医療費は加害者が負担するべきものです。加害者が負担すべき医療費を一時的に国保が立て替え、あとで被害者に代わって加害者に請求するために、必ず届出をお願いします。
9 葬祭費に関すること
Q 国保加入者が死亡したのですが、受けられる給付などありますか。
A 葬祭費(一律5万円)の給付があり、葬祭等を執行した喪主様に支給します。
ただし、国保に加入する前の健康保険から同等の給付が受けられる場合は、国保から葬祭費は支給できません。
10 その他
Q 医療費のお知らせはいつ届きますか。
A 5月(11月、12月、1月、2月診療分)、9月(3月、4月、5月、6月診療分)、1月(7月、8月、9月、10月診療分)の年3回発送します。発送時期は各月末です。
Q 加入者本人以外でも国保に関する手続きはできますか。
A 本人以外でも委任状があれば手続き可能です。委任状は委任した方が記入してください。
なお、同じ世帯のご家族の方であれば委任状が無くてもお手続きできますが、代理人が手続きをする際は、代理人の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要です。