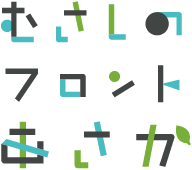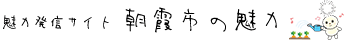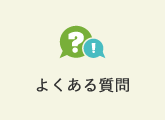本文
マイナンバーカードと健康保険証の一体化(国民健康保険)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
現行の健康保険証の廃止日を定めた政令が交付されたことに伴い、令和6年12月2日以降、再発行を含め、現行の健康保険証は新たに交付されません。マイナンバーカードの健康保険証利用(以下、「マイナ保険証」という。)を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証の登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で事前の登録が必要です。※市役所での登録手続きはできません。
| (1)スマホアプリ「マイナポータル」で行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
| (2)セブン銀行ATMで行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
| (3)医療機関・薬局の受付で行う | 詳しくはこちら(外部サイト) |
マイナ保険証の使い方
マイナ保険証の使い方
医療機関や薬局の受付にある顔認証付きカードリーダーを使用します。
- マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーの読み取り口に置く。
- 「顔認証」を行うか、「暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定した4桁の番号)」を入力する。
- 過去の診療・お薬情報の提供など同意事項を確認する。
- 受付完了
マイナ保険証での受付が出来ない場合
マイナ保険証を利用する際に、何らかの事情で資格確認を行えなかった場合も、以下のいずれかの対応で資格確認を行うことで、ご自身の負担割合で受診することができます。
- マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示
- マイナンバーカードとマイナポータルの画面の提示
- 再診の場合、マイナンバーカードを提示し、医療機関で資格確認に必要な情報を把握していれば、口頭で確認
- 初診の場合、マイナンバーカードを提示し、医療機関で「被保険者資格申立書」を記入する。
DV・虐待等被害者の方へ
DV・虐待等被害者の方は、御自身の情報が閲覧されないようにする届出が必要となります。届出をしないと、加害者に御自身の情報が閲覧される可能性がありますので、加入されている健康保険者へ連絡してください。この届出をすると、(1)マイナンバーカードの健康保険証利用(2)マイナポータルで資格情報、薬剤情報等の閲覧が出来なくなります。
なお、朝霞市の国民健康保険に加入中の方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、市役所内で連携して情報の閲覧を制限するため、個別に届出をする必要はございません。
※朝霞市の住民基本台帳における支援措置を受けている方であっても、会社の健康保険に加入している方は、加入されている健康保険者に届出をする必要があります。
マイナ保険証のメリット
1 より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
2救急現場でも使える
今後、救急現場でも、過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、 搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。
3確定申告の医療費控除が簡単にできます
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
4手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証の解除
朝霞市国民健康保険に加入されている方でマイナ保険証の解除をご希望の方は、保険年金課の窓口で申請することができます。受付後、「資格確認書」を世帯主宛てに郵送します。また、システム上の利用登録については、受付完了後の1~2か月後に利用登録が解除されます。解除完了につきましては、マイナポータルで確認することができます。
※別世帯の方が代理で解除申請する場合は、委任状が必要です。