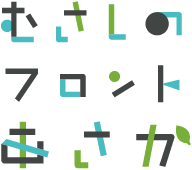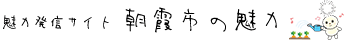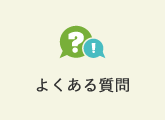本文
保険の給付(★印のある手続きは、支所、各出張所でも受付できます)
- 医療費をいったん全額自己負担したとき・・・ 療養費の支給
- 入院したときの食事代・・・ 入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
- 医療費が高額になったとき・・・ 高額療養費の支給
- 高額な医療費がかかる前の申請について・・・ 限度額適用認定証について
- 医療保険と介護保険の自己負担限度額が高額になったとき・・・ 高額・介護合算制度
- 出産したとき・・・ 出産育児一時金の支給
- 亡くなったとき・・・ 葬祭費の支給
※各申請について、住民登録上、同一世帯以外の方が手続きにくる場合は委任状が必要です。
療養費の支給
次のような場合は、いったん医療費を病院などに全額支払った後、必要書類を添えて申請してください。
|
こんなとき |
申請に必要なもの(ご不明なものはあらかじめお問い合わせください) |
|---|---|
|
事故や急病でやむを得ず国民健康保険の記号番号がわかるものを持たずに治療を受けたとき |
国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか) |
|
本人確認資料 |
|
|
診療内容明細書(レセプト)※診療を受けた際窓口でもらえる「診療明細書」とは異なります。 |
|
|
領収書 |
|
|
世帯主の預金通帳 |
|
|
医師が治療上必要と認めた場合で、コルセットなどの治療用装具を作ったとき (★) 支所、各出張所でも受付できます |
国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか) |
|
本人確認資料 |
|
|
医師の診断書か意見書 *靴型補装具は、装具現物の写真を添付 |
|
|
領収書(詳しい内訳が載っているもの) |
|
|
世帯主の預金通帳 |
|
|
骨折やねんざなどで国保を扱ってない柔道整復師の施術を受けたとき |
国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか) |
|
本人確認資料 |
|
|
診療内容明細書 |
|
|
領収書 |
|
|
世帯主の預金通帳 |
|
|
医師が必要と認めた手術などで輸血したときの生血代(第三者に限る) |
国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか) |
|
本人確認資料 |
|
|
医師の診断書か意見書 |
|
|
輸血用生血液受領証明書 |
|
|
血液提供者の領収書 |
|
|
世帯主の預金通帳 |
|
|
医師が治療上必要と認めた場合で、はり・灸・マッサージなどの施術をうけたとき |
国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか) |
|
本人確認資料 |
|
|
診療内容明細書 |
|
|
医師の診断書か意見書 |
|
|
領収書 |
|
|
世帯主の預金通帳 |
|
|
海外で病気やけがにより、現地の病院で治療を受けたとき |
国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか) |
|
本人確認資料 |
|
|
診療内容明細書(日本語翻訳文を添付) |
|
|
領収明細書(日本語翻訳文を添付) |
|
|
世帯主の預金通帳 |
|
|
パスポート |
|
|
海外の医療機関に照会する同意書 |
入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給
入院時食事療養費
入院中の食事代は、診療などにかかる費用とは別に、次の標準負担額を医療機関の窓口に支払い、残りは国保が負担します。
| 要件 | 食事代 | 必要なもの | ||
|---|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 70歳以上 75歳未満 |
|||
| 住民税課税世帯※(下記以外の人) | 510円 | 510円 | - | |
|
住民税非課税世(オ)低所得者2 |
過去12ヶ月の入院日数が90日までの入院 | 240円 | 240円 | 標準負担額減額認定証を病院の窓口に提示してください。 |
| 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 | 190円 | 190円 | ||
| 低所得者1 | - | 110円 | ||
※所得の申告がない世帯も含まれます。
入院時生活療養費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費にかかる費用のうち次の標準負担額を医療機関の窓口に支払い、残りは国保が負担します。
療養病床に入院する場合の食費
| 要件 | 食費 (1食あたり) |
居住費 (1日あたり) |
必要なもの |
|---|---|---|---|
|
住民税課税世帯(※1) 下記以外の人 |
510円(※2) | 370円 | - |
|
住民税非課税世帯(オ) 低所得者2 |
240円 | 標準負担額減額認定証を病院の窓口に提示してください。 | |
| 低所得者1 | 140円 |
※1 所得の申告がない世帯も含まれます。
※2 医療機関によって470円の場合があります。
標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は標準負担額が減額されます。該当している方は、申請すると「標準負担額減額認定証」が交付されますので、それを必ず国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証のいずれか)と一緒に病院の窓口へ提示してください。
→「標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月末日です。引き続き減額の対象となるためには、再度申請をしていただく必要があります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか)
- 本人確認資料
標準負担額差額支給
やむをえず標準負担額減額認定証の提示ができず減額がされなかった場合は、支払った額と減額後の金額の差額を支給します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか)
- 本人確認資料
- 領収書
- 世帯主の預金通帳
高額療養費の支給
各月ごと(1日~末日)の受診について計算します。
医療機関に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費としてあとから支給されます。ただし、入院中の食事代、差額ベット代などは、支給の対象になりません。
支給対象となる世帯には、診療月の3~6ヶ月後に「高額療養費の支給申請のご案内」をお送りします。それまでは特に手続きの必要はありません。お知らせが届きましたら、市役所国民健康保険係で申請をしてください。
※高額療養費の支給を受けられるはずなのに、お知らせが半年以上届かないなど、ご不安な場合は国民健康保険係までお知らせください。
○高額療養費の自己負担限度額の切り替えは前年の所得に応じ、毎年8月に行います。
- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満の方
70歳未満の方
自己負担限度額は、下記の表のとおりとなります。
一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、診療月の3~6ヶ月後に「高額療養費の支給申請のご案内」をお送りします。申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
なお、入院の場合に支払う一部負担金は、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することにより下記の表の自己負担限度額までとなります。
同じ世帯で、1ヶ月(1日~末日)21,000円以上の一部負担金(同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算)を、医療機関に2回以上支払った場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた額が支給されます。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得※1 | ||||
| 住民税課税世帯 | 上位所得者 (ア) | 901万円超 ※3 未申告世帯 |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 上位所得者(イ) | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
| 一般(ウ) | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
| 一般(エ) | 210万円以下 | 57,600円 | ||
| 住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 | ||
※1 所得とは、総所得金額から基礎控除額(最高43万円)を差引いた金額です。
※2 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額です。
※3 所得の申告がない場合は上位所得者(ア)とみなされます。
○ 70歳未満の方で「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためには、国民健康保険税に滞納がないことが条件になります。
70歳以上75歳未満の方
外来の場合
個人ごと-医療機関ごとの支払いは下記の表の自己負担限度額(1)外来(個人単位)の額までの支払いとなります。さらに、個人ごとに支払った外来の一部負担金を合計し、下記の表の自己負担限度額(1)外来(個人単位)の額を超えた場合、診療月の3~6ヶ月後に「高額療養費の支給申請のご案内」をお送りします。申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
入院の場合
個人ごと-医療機関ごとの支払いは下記の表の自己負担限度額(2)外来+入院(世帯単位)の額までの支払いとなります。
なお、外来・入院の一部負担金は合算対象となり、その合計が下記の表の(2)を超えた場合も診療月の3~6ヶ月後に「高額療養費の支給申請について」のお知らせをお送りします。申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
| 所得区分 | (2)外来+入院(世帯単位) 【B】 | |
|---|---|---|
| (1)外来 (個人単位) |
||
| 現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降※2 140,100円> |
|
| 現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降※2 93,000円> |
|
| 現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降 ※2 44,400円 > |
|
| 一般(課税所得145万円未満等) | 18,000円 <年間上限144,000円※3> |
57,600円 <4回目以降 ※1 44,400円> |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額です。
※2 過去12か月以内に【B】の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 年間(8月~翌年7月)の限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)です。
○ 月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の自己負担限度額は移行前後の医療保険制度でそれぞれ2分の1となります。
その他、「高額療養費委任払い制度」「高額療養費貸付制度」があります。詳しくは国民健康保険係までお問い合わせください。
限度額認定証について
70歳未満の方、70歳以上75歳未満で現役並み1・2世帯の方は、申請により「限度額適用認定証」が交付されます。医療機関に提示することにより外来・入院で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。
住民税が非課税の70歳未満の方及び、70歳以上75歳未満で低所得者1・2の世帯の方は、申請により入院中の食事代の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
70歳以上75歳未満の現役並み3と一般の方は「マイナ保険証」、「資格確認書」で所得区分が確認できるため限度額適用認定証の申請は、必要ありません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか)
- 本人確認資料
有効期限
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月末日です。引き続き必要な方は再度申請をしてください。
高額・介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。
70歳未満の方
| 所得区分 | 限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 所得 | |||
|
住 |
上位所得者(ア) |
901万円超 | 212万円 |
|
上位所得者(イ) |
600万円超901万円以下 | 141万円 | |
|
一般(ウ) |
210万円超600万円以下 | 67万円 | |
|
一般(エ) |
210万円以下 | 60万円 | |
|
住民税非課税世帯 (オ) |
34万円 | ||
70歳以上75歳未満の方
| 所得区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
|
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
212万円 | |
|
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
141万円 | |
|
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
67万円 | |
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
56万円 | |
|
低所得者2 |
31万円 | |
|
低所得者1 |
19万円 | |
出産育児一時金の支給
国民健康保険の被保険者が出産したとき(妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産も含む。)、出産育児一時金が世帯主に支給されます。
支給額
1児につき50万円(ただし、令和5年3月31日以前の場合、1児につき42万円)
出産育児一時金の申請方法
出産育児一時金の申請は、朝霞市国民健康保険に6ヵ月以上加入している被保険者が対象になります。(加入期間が6ヵ月未満でも支給される場合がありますので、詳細については国民健康保険係までお問い合わせください。)
なお、申請方法は以下の3つの方法があります。
(1)直接支払制度
(2)受取代理制度
(3)(1)・(2)以外
- (1)か(2)の制度を利用する場合は、出産費用のうち出産育児一時金の支給額を限度として、市が直接医療機関等に支払いますので、出産費用を一時的に全額支払うといった経済的負担が軽減されます。ただし、医療機関等によってはこれらの制度を利用できない場合があります。
- 他の健康保険で支給される場合には、朝霞市の国民健康保険での申請はできません。
(1)直接支払制度
医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の申請及び受取を保険者(朝霞市国民健康保険)に直接行う制度です。
直接支払制度を利用する場合は、医療機関等が代わりに行いますので申請する必要はありません。ただし、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、保険者に差額を申請することになります。
(2)受取代理制度
医療機関等にご相談の上、あらかじめ保険者に必要な申請を行っていただくことで、出産後に保険者から直接医療機関等へ出産育児一時金の支給額を限度として支払う制度です。
なお、受取代理制度を利用することができる方は、次のすべての要件に該当する方になります。
(1)被保険者の出産について、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2)被保険者の出産について、次のいずれかに該当すること。
ア 出産予定日まで1か月以内であること。
イ 妊娠4か月以上の出産であること。
(3)受取代理について、医療機関等の同意が得られたこと。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか)
- 母子手帳または出生証明書 ※母子手帳の出産者名、出産予定日の記載部分及び妊娠中の経過記録が記載された部分の写し
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) ※必ず医療機関において、「受取代理人の欄」の記入を依頼してください。
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 世帯主の預金通帳の写し
(3)直接支払または受取代理制度を利用しない場合 (★)支所、各出張所でも受付できます
出産予定の医療機関等から、事前に直接支払制度または受取代理制度を利用するかどうか確認されますので、利用されない場合は、医療機関等との直接支払制度等の合意文書に「利用しない」旨を記載し、出産後、市に申請してください。確認後、口座振込にて出産育児一時金を支給いたします。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面のいずれか)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 母子手帳 ※出生届出済証明及び出生の状態の記載されている欄の写し
- 医療機関等からの出産費用がわかる領収・明細書 ※産科医療保障制度加入機関の印のあるもの
- 医療機関等と交わした直接支払制度の利用についての合意文書 ※合意文書に「直接支払制度を利用しない」旨の記載のあるもの。
- 世帯主の預金通帳の写し
葬祭費の支給 (★)支所、各出張所でも受付できます
国民健康保険に加入している方が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
なお、国民健康保険に加入してから3ヶ月以内に亡くなられた場合は、国民健康保険加入前の保険から支給されます。
支給額
5万円
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書 [PDFファイル/94KB]※【記入例】葬祭費支給申請書 [PDFファイル/163KB]
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
- 会葬礼状等または葬儀費用の領収書 ※亡くなられた方と葬祭執行人の名前が記されているもの
- 葬祭を行った方の預金通帳の写しと本人確認書類 ※運転免許証など
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。