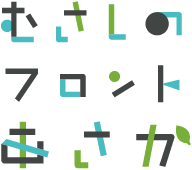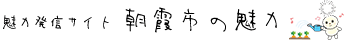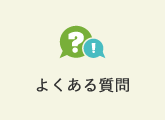本文
ふるさと朝霞の歴史(6)武蔵武士と板碑
武蔵武士と板碑
9世紀から10世紀にかけて、東国では荘園を管理していた人々などが武装した集団を作り、棟梁と呼ばれる有力者がその集団を統率しました。武士団の誕生です。
武士たちは、源平の争いなどを通じて勢力を伸ばし、鎌倉時代になると鎌倉幕府に仕える御家人として、将軍から与えられた領地を支配し、自分の領地を守るため、「一所懸命」に働きました。また、仏教を厚く信仰し、仏像を作って寺院に納めたり、板石塔婆を建てたりして、死後の極楽往生を願いました。
朝霞を拠点としていた武士にどのような人がいたか、はっきりとはわかっていませんが、鎌倉時代に造られた鉄仏が根岸台の台雲寺に伝えられ、朝霞市指定有形文化財になっています。
また、鎌倉時代から室町時代にかけて作られた板石塔婆が、岡の東圓寺や膝折町の一乗院などに残されており、市内全域ではおよそ800基もの数を数えます。この時代の人々の信仰の様子を今に伝えるとともに、武士が活躍していたことを示す資料となっています。
室町時代には、政治の中心であった京都での戦乱(応仁の乱)をきっかけとして、全国に戦いが広がりました。
武士たちは自らの拠点となる城や館を築き、それらは戦いの時の攻撃と防衛の拠点にもなりました。
黒目川を臨む舌状台地に築かれた「岡の城山」は、この時代の城跡の1つで、太田氏に関係する城との伝承があり、現在でも空堀や土塁がよく残されています。

岡の城山(埼玉県選定重要遺跡)
この時代に関東地方などを旅した道興准后が記した紀行文「廻国雑記」の中に、朝霞市の辺りのこととして「膝折の市」という言葉があり、この当時、既に旅人が行き交うような道ができていたことと、市が開かれるような場所であったことがわかります。