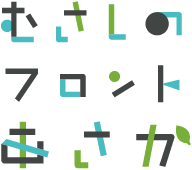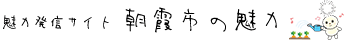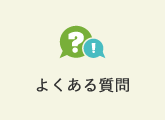本文
成年後見制度のご案内
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより、財産の管理や必要な福祉サービスの利用契約を結ぶことが難しい方々のために、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、ご本人に代わり、ご本人の意思を尊重した上で、心身の状態や生活状況に配慮しながら個人の権利を守り、生活を支援するための制度です。
成年後見制度は次の2種類があります
任意後見制度
将来、判断能力が衰えたときに備えて、「誰に何を頼みたいのか」などをあらかじめ決めておく制度です。判断能力があるときに、公証役場で公正証書を作成して、任意後見人となる人(任意後見受任者)と任意後見契約を締結しておきます。
判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申立てを行うことにより任意後見監督人が選任され、あらかじめ決めておいた任意後見人が、本人のために活動を開始します。
たとえばこんな時・・・
- 将来認知症になったり、病気で倒れたときに、介護に関することなどの手続きを誰かに頼みたい
- まだ判断能力はしっかりしているが、ひとり暮らしのため将来が不安 など
法定後見制度
既に判断能力が低下している方のための制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの支援内容に分かれ、本人や親族等の申立てにより、家庭裁判所が本人の支援者として適切な方を選任します。
| 後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 本人の状態 | 常に判断能力が欠けている | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
| 支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
| 申立できる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など | ||
| 代理権の範囲 | 原則すべての法律行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為 |
| 同意権の範囲 | - | 民法で定められた行為(借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築など) | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為 |
| 取消権の範囲 | 日常生活に関する行為(日用品の購入等)以外のすべての行為 | 民法で定められた行為(借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築など) | 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為 |
たとえばこんな時・・・・
- 預貯金の引き出しなど、金融機関での手続きが自分ひとりでできない
- 訪問販売や悪徳商法の被害に何度もあっているので防止したい
- 知的障害の子どもに関する手続きは、親である自分が行いたい。そして、自分が死亡した後は安心できる人にみてもらいたい など
こんな支援を行います(できないこともあります)
契約により異なりますが、成年後見人等は、次のような法律行為をご本人に代わって行ったり、不利益な契約について取り消したりすることができます。
財産管理(ご本人の預貯金や不動産など、財産の管理や契約に関する支援)
- 年金などの収入と公共料金などの支出の管理
- 不動産などの財産の管理・保存・処分
- 預貯金の預入れ、払戻し、定期預金の解約 など
身上監護(日常生活の維持と向上のための各種申請や、福祉サービスの契約に関する支援)
- 老人ホームなどの施設入所や介護サービスに関する契約締結
- 介護保険などの制度利用手続き
- 福祉サービスに関する希望の代弁 など
手続きと費用
申立ての手続き
この制度を利用するためには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(朝霞市は「さいたま家庭裁判所」)に申立てをする必要があります。
申立てに必要な書類がありますので、あらかじめ家庭裁判所で確認が必要となります。
※申立書式や申立て手続きに関しては、以下のページをご確認ください。
- さいたま家庭裁判所後見サイト(外部サイト)
- 成年後見制度を利用される方のために [PDFファイル/1.2MB](裁判所発行)…家庭裁判所の手続きの流れなどについて、簡単に図解したものです。
利用するために必要な費用
申立てに必要な費用
申立てにかかる収入印紙や郵便切手など(合計約1万円)のほか、申立て用の診断書を作成するために費用がかかります。また、家庭裁判所の判断によりご本人の判断能力を医学的に判断するため、鑑定を行うための費用が必要となる場合もあります。
成年後見人等が選任されてから必要な費用
成年後見人等への報酬の支払いが必要となります。ご本人の資産などの状況を見て、家庭裁判所が報酬の金額を決めます。
申立て前に注意すること
※一度申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。たとえば、申立人が希望する人が成年後見人等に選ばれそうにないという理由では、原則として取下げは認められません。
成年後見制度に関する相談窓口
「成年後見制度に関する相談窓口」のページをご覧ください。
もっと詳しく知りたい方は
パンフレット
●裁判所が発行しているもの(裁判所ホームページ(外部サイト))
- 成年後見制度-利用をお考えのあなたへ- [PDFファイル/3.28MB]…家庭裁判所における手続きや成年後見人の仕事などについて、詳しく説明したものです。
- 後見制度において利用する信託の概要 [PDFファイル/2.36MB]…後見制度信託を利用する場合の手続きなどについて説明しています。
●法務省が発行しているもの(法務省ホームページ(外部サイト))
この他、市が発行しているパンフレットは、福祉相談課・地域包括支援センター・各公共施設で配布しています。
外部サイト
厚生労働省ホームページ「成年後見はやわかり」(外部サイト)