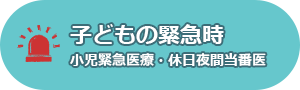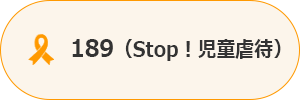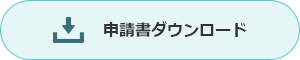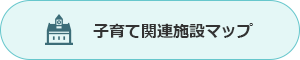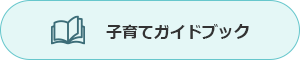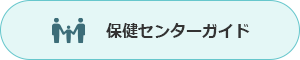本文
児童扶養手当
※手当を受給するためには、申請が必要です。
児童扶養手当について
趣旨
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給対象者となる方
(1)次の項目のすべてにあてはまる方が受給対象者です。
- 朝霞市に住民登録(居住の実態)がある方
- 満18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
※対象児童が、一定の障害の状態にある場合は、20歳未満
(2)養育する児童について、次の項目のいずれかにあてはまる方が対象です。
- 父母が婚姻(または事実婚)を解消している児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童(詳しくはこちらをご覧ください)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(事実上の婚姻状態にある場合を除く)
- その他の理由で父または母がいない児童
(3)支給されない場合
- 父または母が事実上の婚姻状態にあるとき(事実上の婚姻関係とは、原則異性と同居している状態をいいますが、異性の住民票が同住所にある場合や、同居はしていないが頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的な生活費の補助を受けている場合を含みます。)
- 対象となる児童が国内に住所を有しないとき
- 対象となる児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき
※ ただし、年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は、差額を受給できます。 - 対象となる児童が里親に委託されているとき
- 対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されているとき
※ 上記に記載がなくても、状況によって支給されない場合がありますので、ご不明な点がありましたら、こども未来課にご相談ください。
手当を受給するための手続き等
手当を受給するには、請求者(児童を養育している父、母、または養育者)本人が認定請求を行う必要があります。
認定請求の際には、次のものをご用意ください。なお、必要書類は認定請求書提出後でも提出可能な場合があります。受給資格や必要書類については事前にこども未来課にご確認ください。
※手当は認定請求書提出月の翌月分から受給対象となります。さかのぼって受給を開始することはできませんので、受給事由が発生したらすみやかに手続きをしてください。
必要書類等
1.請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
※ただし、戸籍の届出後間もないため戸籍謄本を取得できない場合は、受理証明書で仮受付ができます。
2.請求者名義の振込先口座のわかるもの
3.年金手帳
4.請求者及び対象児童の健康保険情報がわかるもの(ひとり親家庭等医療費の手続きに使用します)
※その他、状況によって必要書類の提出を求める場合があります。
手続き窓口
請求者の生活状況等をお伺いしながらご案内しますので、必ずご本人がこども未来課にお越しください。手続きには1時間程度かかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
なお、支所・出張所では、請求及び相談は受けられませんのでご了承ください。
手当額
所得制限限度額未満の場合、所得に応じて全部支給または一部支給となります。
| 児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 46,690円 | 所得に応じて 46,680円 ~11,010円 |
| 2人目以降加算額 | 11,030円(1人につき) |
所得に応じて 11,020円 ~ 5,520円(1人につき) |
令和6年11月分~令和7年3月分の月額(制度改正後の最初の支給月:令和7年1月)
所得に応じて 10,740円 ~ 5,380円(1人につき)
| 児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 45,500円 | 所得に応じて 45,490円 ~10,740円 |
| 2人目加算額 |
10,750円 |
所得に応じて 10,740円 ~ 5,380円 |
| 3人目以降加算額 | 6,450円(1人につき) | 所得に応じて 6,440円 ~ 3,230円(1人につき) |
支給時期
手当は1年に6回、奇数月の11日(祝・休日に当たる場合は直前の開庁日)に、2か月分ずつ支給されます。
| 支給月 | 1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給内容 | 11・12月分 | 1・2月分 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 | 9・10月分 |
※受給資格の喪失手続き等により、上記の指定月以外に随時で支給することがあります。
所得制限限度額
請求者本人や配偶者、同居している扶養義務者の所得を下記の所得制限と比較することで支給区分(全部支給・一部支給・全部停止)が決定します。所得が所得制限限度額以上の場合には全部停止となり、手当を支給することができません。
なお、1月から9月の間での請求は前々年、10月から12月の間の請求は前年の所得で審査します。対象児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、受取額の8割相当を本人所得に加算します。詳しくはこども未来課へお問い合わせください。
| 税法上の扶養人数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
※扶養人数が1人増えるごとに、限度額が38万円加算されます。
※所得から、8万円の一律控除のほか、諸控除(医療費控除、雑損控除等)を受けられる場合があります。
※児童扶養手当の認定請求が1月から9月の場合は前々年、10月から12月の場合は前年の所得で審査します。(ひとり親家庭等医療費は、1月から6月の間の認定請求は前々年、7月から12月の認定請求は前年の所得で審査します。)
※所得制限の判定は、給与所得および公的年金等に係る所得の合計額から10万円が控除されます。
支給区分の例
(1) 受給者:所得450,000円、税法上の扶養0人 → 全部支給の所得制限未満
同居の受給者の母:所得3,000,000円、税法上の扶養2人 →所得制限未満
→ 全部支給に該当
(2) 受給者:所得800,000円、税法上の扶養0人 → 一部支給の所得制限未満
同居の受給者の母:所得1,980,000円、税法上の扶養0人 →所得制限未満
→ 一部支給に該当
(3) 受給者:所得960,000円、税法上の扶養0人 → 一部支給の所得制限未満
同居の受給者の母:所得2,440,000円、税法上の扶養0人 →所得制限以上
→ 扶養義務者の所得超過により全部停止に該当
現況届
受給者は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届を審査することで、受給資格の有無や、その年の11月分から翌年の10月分までの支給区分及び支給額が決まります。現況届については7月下旬にご案内を送付しますので、必ず内容をご確認ください。提出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当が支給できなくなることがありますので、提出期限にご注意ください。
※前年度の手当が全部停止だった方も、現況届の提出義務があります。
資格喪失について
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出を行う必要があります。
- 受給者である父または母が婚姻した場合(事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者が児童を監護または養育しなくなった場合
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
- 児童が父(受給者が母または養育者の場合)または母(受給者が父の場合)と同居するようになった場合
- 児童が児童福祉施設等に入所した場合
- 児童を遺棄していた父または母が帰宅した場合や連絡があった場合
- 拘禁されていた父または母が出所した場合
- 受給者または児童が死亡した場合
- その他、手当を受ける資格がなくなった場合
※受給資格がなくなっているにもかかわらず、届け出をせずに手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただくことになります。
その他必要な届出について
児童扶養手当の受給者の方(支給停止中も含む)で、次のような場合には、届出が必要です。
- 住所を変更した場合
- 氏名や児童扶養手当の振込先の金融機関口座を変更した場合
- 扶養義務者と同居・別居するようになった場合
- 対象児童に増減があった場合
- 公的年金を受給するようになった場合
- 児童扶養手当証書を紛失した場合(再交付には1か月程度かかります)
一部支給停止適用除外届出について(法第13条の3関係)
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の自立を支援することを目的に支給される手当であることから、支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、または、支給開始月の初日から5年が経過したときは、手当の額が2分の1になります。(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年経過したとき。)
ただし、自立に向けた就業や求職活動の状況、または、就業できない理由などを確認させていただき、適用除外事由に該当する場合は、期限内に「一部支給停止適用除外事由届出書」をご提出いただくことで、一部支給停止の適用を除外することができます。
対象の方には届出書等を送付しますので、必ず内容をご確認のうえ、ご提出ください。